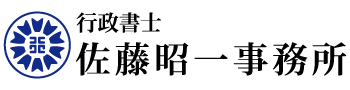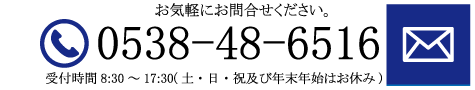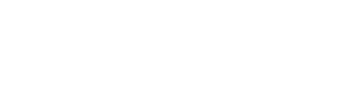行政書士の佐藤 昭一です。
新年度が始まりました。食料品の値上げや子ども・子育て支援法の改正、育児・介護休業法の改正など様々動きがあります。そうした動きの中で今回はカスハラ防止条例について取り上げたいと思います。長文になりますが、よろしくお願いします。
皆さんは、日頃生活を営んでいく中で、「これってカスハラじゃない?」と思われる現場やSNSの投稿、TVのニュースで見たことがあるんじゃないか思います。こうした事案が多数発生している現状を踏まえて、自治体においてもカスハラ防止条例を制定施行する動きが出ています。
4月1日から東京都・群馬県・北海道で条例が施行されました。愛知県・三重県は条例施行する方針で動いており、岩手・栃木・埼玉・静岡・和歌山の5県でも条例制定に向けた検討をスタートしています。
三重県桑名市は悪質なカスハラに対してはカスハラ当事者の氏名を公表できるカスハラ防止条例を既に施行しています。(この条例については、賛成と反対の両方の意見があったようです。)
さて、カスハラとはいったいどういった行為なのか改めて以下のとおりお話しします。
①カスハラの正式名称は「カスタマーハラスメント」と言います。日本語に訳すと「お客様からの嫌がらせ」と言ったところになるかと思います。
②カスハラの定義について
お客様が従業員に対して、不適切な言動や過剰な要求をすることにより、従業員に心と身体に多大な負担をかける行為を行うこととされています。
③カスハラ行為の具体例について
以下のことが挙げられます。
理不尽な苦情やクレーム・威圧的な態度・無理な要求・暴言や暴力・セクハラまがいの言動・土下座を 要求する・ネットに拡散すると脅すなどが挙げられます。いずれも要求するやり方が世間一般常識から大きくかけ離れている行為であり、悪質かつ深刻なものは刑事罰の対象にもなります。
④事業所の取り組みについて
事業所は安全配慮義務に基づいて従業員を守る責任がありますので、カスハラに対する対応マニュアルの策定やそれに付随して関係する機関との連絡体制の整備を行っています。お客様へのカスハラに関する周知方法として、よく飲食店やコンビニの入口やレジ前にカスハラに関するガイドラインのポスターが掲示してあります。こうした取り組みもカスハラから従業員を守る対策の1つだと思います。
⑤クレームとカスハラの違いって何?
クレームとカスハラの違いがわかりにくいとの話しが出ることがあります。できる限りわかりやすい例を用いて私なりにお話ししてみたいと思います。クレームについては、難しい表現で表すと「お客様が店舗や事業所に対して正当な(ここが大事なポイント‼️)要求や改善を提案すること」を指します。
わかりやすい例として、お客様が買った商品の不具合を見つけ指摘したうえで商品の交換をお願いする行為は正当なクレームに当たります。それ以外の行為は、ほぼカスハラに当たると考えます。(「③カスハラ行為の具体例について」を参照していただければわかりやすいかと思います。)
最後に、カスハラは誰もが当事者や被害者のどちらかの立場になる可能性がある行為です。他人事と考えずに自分事と考えてみてはいかがでしょうか?私もカスハラについて、十分に配慮し気をつけるよう心がけていきます。