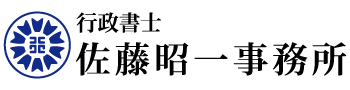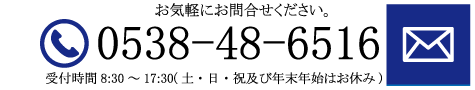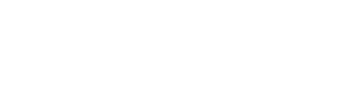行政書士の佐藤昭一です。前職ではスポーツに関する業務に携わったことは、部活動の地域移行についてをテーマにお話しした時に触れさせていただきました。
行政書士の話しから外れてしまいますが(またですかはナシで・・・(汗))、皆さんは登山はレジャーだと思いますか?それともスポーツだと思いますか?私は両方の側面があると考えています。
4月に富士山で閉山期間中に登山し2回も遭難した中国人留学生に対して救助にかかった費用を請求すべきとの意見がSNS上で多数投稿されています。(登山目的が山頂にアイゼンと携帯電話を忘れたので、取りに行くために2回登山したとの個人的な理由がより悪い印象に拍車をかけたようです。その後、中国人留学生は「二度と登山はしません」と謝罪したようです。)
今回は閉山期に遭難した場合の遭難救助費の負担のあり方について、スポーツ関係の業務に携わったものとして私なりの考え方をお示しできればと思います。
今回の閉山期間中の登山者の遭難救助について、静岡県側の富士宮市長は「遭難救助費用は遭難者の自己負担として有料にするようルール作りをすべきで、県へ要望する。」との見解を示しています。(山梨県側の富士吉田市長も同じ見解のようです。)静岡県知事は、「ルールを逸脱した登山での負担については議論の余地がある」との見解を示したが、遭難救助費用の遭難者の自己負担については、県として国に検討をお願いするスタンスのようです。
現状は、閉山期間中にゲートを乗り越えての登山や開山期間中の真夜中に弾丸登山をするなど、ルールやマナーを無視する行動が後を絶たない状況にあります。軽装で登山する方もいるようで、登山の際の準備の重要性や登山マナーをしっかり理解していないようです。
静岡県では今年度から開山期間中の富士登山の際に事前登録アプリを使って登山は予約制を採用し、登山に関するルールや注意点を示した研修を受講しないと登山が出来ない仕組みを作りました。また入山料も確か4000円だったと思いますが、クレジット決済での支払いにするなど、一定の対策をとっています。
問題は閉山中の登山についてです。閉山中に登山者が遭難した場合の遭難救助費用は我々が納めている税金から支出されています。(山岳救助隊の編成やヘリコプターの費用など)費用も多額であり自治体の費用負担はかなりのものになります。
私の個人的な私見としては、遭難救助費用は自己負担を原則とするのが良いと考えます。登山者が遭難した場合には、多額の費用がかかることを自覚してもらい自己責任の重さを認識してもらう必要があると思います。あと、着眼点は違いますが、登山者に対して山岳保険の加入を推奨することもひとつの方法だと思います。(1日保険のプランもあるようです。)
最後に、富士山は海外からの登山客も多くオーバーツーリズムの傾向が見られます。登山のマナーやルールを守ることが出来ない方やルール違反を繰り返して改善出来ない方は、今後は登山を禁止もしくは自粛してもらうことを考えざるを得ない時期に来ているのかもしれません。